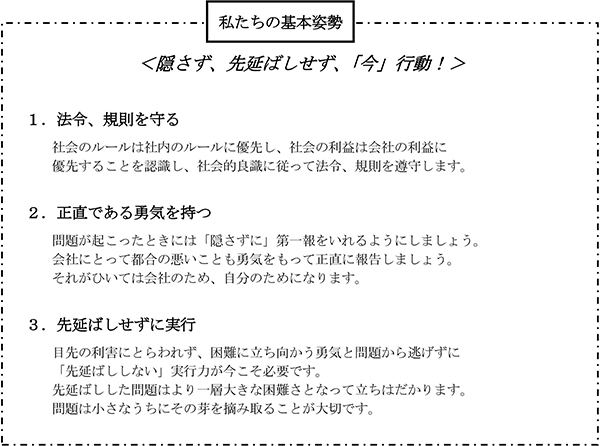コンプライアンス
基本的な考え方と推進体制
JVCケンウッドグループは、コンプライアンスについて、法令遵守に留まらず、急激な世の中の変化に対して、法令化されていなくても、社会的な要請が高い課題への対応も含むと理解しています。この基本的な考え方のもと、CEOを委員長とするコンプライアンス委員会と法務・コンプライアンス室内部統制グループの主導により、「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」にのっとり全社的に推進しています。
コンプライアンス行動基準
「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」(2010年3月制定)は、冊子(3か国語対応)とイントラネットを通じて、当社グループ内の全役職員に周知されています。また、傘下の関係会社については、当社取締役会で選任された「コンプライアンス担当役員」を通じて各従業員へ周知徹底されています。
法務・コンプライアンス室内部統制グループは、「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」の遵守状況については随時確認を行い、毎年度その結果を取締役会に報告するとともに、従業員などからの問い合わせに対応しています。
コンプライアンス推進に係る具体的な取り組み
コンプライアンス行動基準の遵守
JVCケンウッドグループでは、「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」および諸規程を整備するとともに、コンプライアンス委員会および法務・コンプライアンス室内部統制グループにより、グループ全体のコンプライアンス行動基準の遵守状況をモニタリングする体制を構築しています。また、関連法令の改正状況などを踏まえ、コンプライアンス行動基準の有効性を年に1回レビューしています。
コンプライアンス違反の防止に向けては、内部通報システムの設置や、コンプライアンス研修を行い、グループ全体のコンプライアンス意識の醸成を図っています。内部通報システムにより、コンプライアンス行動基準の逸脱や腐敗行為、法令違反、企業倫理上の違反などの通報を受け付けています。内部通報システムにコンプライアンス違反に関する通報があった場合、およびその懸念が生じた場合は、内部通報システム窓口および関係する部門において通報内容の事実確認を行います。その結果、コンプライアンス上問題があると認められた場合には、コンプライアンス委員会にて内容を精査し、違反内容に応じて適切な是正措置をとり、再発防止策を実施します。また、是正措置の内容は通報者に報告するとともに、関係者名を伏せたうえで、違反内容について社内に周知するなどし、同様の事案の再発防止を図ることとしています。なお、2024年度に発生した法令違反およびコンプライアンス違反に関する通報事案は3件で、必要に応じて社外の専門家との相談・協議等を得た上で、全ての事案についてコンプライアンス委員会で審議し厳正に対処しました。また、対象者への対処だけにとどまらず、関連ジャンルの研修の実施・意識調査等によるモニタリング・窓口の社内認知度向上に向けたイントラネットへの案内掲載・メールマガジンの配信・ポスターの掲示等を実施し、全社的な啓発により不正リスクとしての認識を深め、再発防止を図っています。
JVCケンウッドグループの税務方針(2024年6月策定)
JVCケンウッドグループは「感動と安心を世界の人々へ」提供するという企業理念をグループの行動の原点として共有し、この理念にもとづき、高い収益性を確保するとともに企業としての社会的責任を果たすことにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでいます。これは、法令、企業方針、社会慣習、および正しい企業倫理の遵守によって実現されると考えます。
1.税務に関する基本方針
JVCケンウッドグループは、各国の税法およびその他OECD(経済協力開発機構)等の国際機関が公表している租税に関するガイドラインにも準拠し、正しい納税に努めてまいります。また、法令等の立法趣旨を逸脱する解釈による優遇税制の適用や、事業実態のない意図的な租税回避行為及び軽課税国を利用した濫用的な税務プランニングは行いません。
2.税務ガバナンス
JVCケンウッドグループにおける税務ガバナンスは、当社の財務担当役員が管轄し、その実務運営は税務担当部門が税務に関する処理、確認、報告、管理を行う体制としており、より専門性の高い事案に対しては外部専門家の意見も取り入れています。また、グループ各社の税務コンプライアンスに対する意識向上を図るため、適切な経理処理や税務処理に関する社内での教育・啓発活動と税務相談体制を整備する取り組みを推進してまいります。
3.タックスプランニング
グローバルに展開する当社グループの事業活動に於いて、株主価値の最大化の観点から、各国における税制優遇を積極的に活用してまいります。但し、基本方針にある通り、各国の法令等の考えを逸脱した税回避行為は行いません。また、今後施行されるGloBEルール(グローバル・ミニマム課税)等、税制における課税の考え方を十分に理解し、対象となる場合には適切な申告納税を行います。
4.税務リスク低減とモニタリング
グループ各社の税務執行状況の定期的モニタリング及び情報交換、各種報告を通じて税務リスク認識、必要な是正、運用支援を行っています。また、事前のリスク把握に努め、リスク発現前の対策や、外部専門家からの助言、税務当局への確認などにより税務リスク低減に取り組んでいます。
腐敗防止に関する取り組み
JVCケンウッドグループでは、取締役会による監督のもと、「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」および社内規程において、贈収賄を含むあらゆる腐敗行為を一切禁止していることや、他者の行動に影響を及ぼすために違法または不適切な手段を用いてはならないことを明文化しています。腐敗行為防止に関連する法令を遵守することはもちろん、会社の財産や他人の所有物の搾取といった贈収賄・横領、業務を利用した不当な金品その他の利益の授受といった利益供与の強要等の腐敗行為を禁止しています。
上記のような腐敗行為に関しては、JVCケンウッドグループおよび取引先を対象として、腐敗リスクを評価することとしています。
JVCケンウッドグループに関する腐敗リスクの評価については、全部門にて毎年実施するリスクサーベイランスにおいて実施しています。リスクサーベイランスにおいては、不当な接待・贈答といった行為がないか確認し、その結果を踏まえて社内規定の見直しや腐敗防止のための取り組み強化につなげています。
取引先に対しては、当社グループが取引先に順守いただきたい事項をまとめた「JVCケンウッドCSR調達ガイドライン」において、腐敗防止に関する事項を定めています。パートナーズミーティングにて定期的に周知するほか、既存の取引先に対しては自己評価シート(SAQ)への回答を通じて、腐敗リスクを評価しています。
また新規取引先との契約時には、反社会的勢力排除のための事項として、反社会的勢力であるもしくは反社会的勢力と関わりがあると判明した場合の契約解除を明記しているほか、新規取引先申請書にて法令順守のための仕組みの構築・法令違反の有無を確認するなど、贈収賄などの腐敗防止に取り組んでいます。
なお、贈収賄やファシリテーション・ペイメントなどの腐敗行為に対しては、コンプライアンス研修およびeラーニング、イントラネットによる情報発信を行い、腐敗防止について周知徹底を図るといった取り組みを行っています。
贈収賄や汚職などの重大なコンプライアンス違反については、コンプライアンス委員会にて再発防止の対策などについて審議、議論を行います。また、贈収賄や汚職を含む全ての不祥事案は、取締役会に報告されます。なお、2024年度に腐敗行為により法的措置を受けた事例はありません。
また、企業活動の透明性を確保することも重視しており、例えば特定の政党や団体に対する献金などを含む情報開示についても進めていく方針です(2024年度の政治献金額:0円)。
ハラスメント防止に向けた取り組み
2020年6月から「パワハラ防止法」(労働施策の総合的な推進ならびに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が施行されていることに伴い、事業主のハラスメント防止義務の認識を社内に浸透させるため、従業員向けにハラスメント研修の実施やイントラネットによる情報発信を行っています。
通報システム
■従業員向け通報窓口
JVCケンウッドグループでは、内部通報システムとして法務・コンプライアンス室に設置された「JVCKENWOODヘルプライン(以降、「ヘルプライン」)」と、監査等委員会室に設置された「監査等委員会ホットライン」の2つを整備しており、全ての役職員(契約社員を含む)が使用することができ、匿名での通報も受け付けています。「ヘルプライン」は電話通報とWeb通報の2つで構成され、外部機関である内部通報窓口サービス会社が第三者窓口として通報内容を受け付ける仕組みとなっています。(日本語、英語、中国語、韓国語で対応)
人権侵害やハラスメント、あらゆる形態の腐敗行為(横領、贈収賄など)といった企業倫理全般やコンプライアンス上の懸念が生じた場合は、「内部通報規程」に基づき「ヘルプライン」に直接通報される仕組みとなっており、事実確認作業を経てコンプライアンス委員会主導のもとで是正措置がとられます。また、役員などの不正については、「監査等委員会ホットライン」へ直接通報され、適切な対応をとることとなっています。全てのシステムは専用の通信インフラとして運用されており、通報内容および通報者は厳重に守られ、通報者が不利益を受けることはありません。
■外部ステークホルダー向け通報窓口
JVCケンウッドグループでは、外部のステークホルダーからの当社に係る法令・社則違反等の通報は、一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)※1が提供する苦情・通報窓口にて受け付けています。
当社が正会員企業として参加する一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)にて提供されている苦情・通報窓口では、匿名の通報が可能となっています。通報受付後は同法人により提起された対応案や支援のもと、是正や再発防止の措置を講じています。
※1 一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)は、「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠して非司法的な苦情処理プラットフォームである「対話救済プラットフォーム」を提供し、 専門的な立場から会員企業の苦情処理の支援・推進を目指す組織です。
今後もこれらのシステムの活用により、コンプライアンス違反(社会的要請を逸脱した行為)の早期発見と是正に努めていきます。
コンプライアンス研修
コンプライアンスに関する教育は、CEOの指示のもと法務・コンプライアンス室内部統制グループが主管しており、海外グループ会社27社を含む、全役職員へ周知徹底することにより、強固なコンプライアンス体制の構築に努めています。新入社員研修においては対面で、それ以外の従業員はeラーニングで定期的に研修を行い、同時にコンプライアンス意識の浸透度を確認するためのアンケートも実施しており、行動基準の理解度のチェックやコンプライアンス活動に対する意見を集めています。2024年度に実施したアンケートでは、約3,250人の役職員から回答が得られました。
また、コンプライアンス担当役員による研修も年1回実施され、当該役員直下の部門長や経営幹部を対象としてコンプライアンス行動基準やその他関連規程、ファシリテーション・ペイメントや外国公務員への贈賄禁止、過度な贈答品の授受禁止などを含む腐敗防止、不正競争防止、企業不祥事事例、内部通報制度といったトピックを取り扱っています。こうした各種の研修を通じ、2024年度は約5,800人の役職員がコンプライアンス研修を受講しています。
そのほかにも、コンプライアンスの意識向上と啓発を目的に、2018年度より役職員に向けてコンプライアンスに関するメールマガジンを月1回配信するとともに、イントラネットにコンプライアンスに関するコンテンツを掲載・更新しています。また世の中で起こっているコンプライアンス違反の事例やその月のコンプライアンスニュースをわかりやすく解説するとともに、コラムやケーススタディクイズなどを用いて意識付けできるように工夫し、啓発活動を行っています。
監査等委員会のコンプライアンスへのコミットメント
JVCケンウッドでは、監査等委員会が不正の発見、内部統制の評価、法規制の遵守状況の監視などを含む経営監査の機能を担っています。なお、監査等委員である取締役の任期は会社法により2年と定められており、任期満了時に定期的にローテーションが行われています。監査等委員は、独立の立場および公正不偏の態度の保持に努めて監査を行っています。
内部監査について
当社における内部監査は、内部監査室が当社グループ全体への執行業務に対する内部監査と、財務報告に関わる内部統制評価(J-SOX評価)を、取締役会の承認に基づく監査計画により実施し、これを監督機関である取締役会へ報告しています。内部監査室は、現在13名が内部監査およびJ-SOX評価に従事しています。内部監査室は、当社および当社グループ関係会社まで幅広く、往査もしくはリモート監査を行い、内部統制状況のモニタリングを一元的に実施することにより、企業統治システムの有効性および効率性、コンプライアンス、他の内部統制システムおよびその実施状況、事業活動などについて、リスクベースで客観的な評価を行い、その結果に基づく情報の提供、改善に貢献する有益な提言を通じて、当社グループ全体の社会的信頼性の確保・維持に寄与しています。
監査法人による会計監査人の定期的なローテーションおよび再関与について
JVCケンウッドグループでは公認会計士法等に基づく監査法人の規程にのっとり、次のとおり会計監査を行う業務執行社員の定期的なローテーションが監査法人によって行われていることを確認しています。
- 原則として業務執行社員は連続して7会計期間、筆頭業務執行社員は連続して5会計期間を超えて当社監査業務に関与することができない。
- 原則として業務執行社員は交替後2会計期間、筆頭業務執行社員は交替後5会計期間、再度当社監査業務に関与することができない。
監査法人の選定、および評価について
当社は現在も、当社会計監査人である監査法人が当社グループの理解とリスク領域の把握と対応、品質管理体制、独立性、監査計画の策定方針と内容、ネットワーク・ファームを含めたグループ監査の状況、不正リスクへの対応及び監査報酬の合理性等を評価しており、事業環境の変化等をはじめとした種々のリスクを抱える当社の監査法人として、必要な水準を満たしていると判断しております。
また、当社は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を以下のように定めています。
「監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当するときは、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任し、また、監査等委員会は、原則として、会計監査人が監督官庁から監査業務停止の処分を受けるなど当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。」
監査等委員会は、毎年、監査等委員会で定めた「会計監査人の選解任に関する評価基準」に従い評価を行い、さらに前述の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」も踏まえ、監査法人の選解任の必要性について検討しています。監査等委員会は、現在の監査法人について、本基準に基づく適格性評価及び「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく検討の結果、問題が無いものとして再任が妥当と判断しています。