【JVCKENWOOD NEWS】
Through Tak's Eyes
SDGsの「ZERO HUNGER」
当社を含め各企業はSDGsへの取り組み・対応を強化しています。
このSDGsは、2015年9月に国連総会で採択された17のグローバルな持続的開発目標(ゴール)と、169の達成基準(ターゲット)で構成されており2030年での達成を目指しています。SDGsの前身は、2000年9月に開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と、1990年代にサミットを含む主要な国際会議で採択された開発目標を統合した「ミレニアム開発目標(MDGs: Millennium Development Goals)」です。従来、大企業を中心にいわゆるCSR (Corporate Social Responsibility) としてさまざまなメセナ活動や寄付活動が行われてきましたが、SDGsへの対応では、各企業がそれぞれの事業をSDGsに直結させて持続的に活動する姿勢が顕著になってきています。
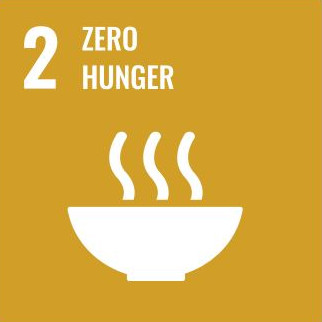
17の目標はそれぞれとても大切なものですが、2番目の「飢餓をゼロに(ZERO HUNGER)」は最も重要なゴールの一つであると同時に、日本に住んでいる我々には最も実感が得にくいゴールでもあります。さらに、当社のようなエレクトロニクス企業は事業直結の重点目標として採択しづらいものであることも事実です。
日本を含む先進各国では「飽食」の文化があり、膨大な食糧廃棄と食品ロスが発生しています。一方、アジア、アフリカなどの発展途上国や難民キャンプでは日々の食事にも事欠く環境となっています。
世界の飢餓人口は2005年の8.26億人(世界人口比12.6%)から漸減し、2014年には6.29億人(同8.6%)に減少したものの、以降は一進一退が続き、2017年から増加傾向となり2019年には6.88億人(同8.9%)となっています。現状では2030年にはさらに増加し8.41億人(同9.8%)になる見通しとなり、「飢餓をゼロに」は大きく後退しています。
世界の食糧生産は1940~1960年代の「緑の革命」以来、化学肥料により収量が年間約43億トンにまで増大していますが、その30%の約13億トンが廃棄されています。食料廃棄とは食料として消費されず実際に廃棄されたものをいいます。多くは、先進国においては規格外、加工品の形状不備、価格維持のための間引き・廃棄、売れ残りなどが原因となっており、途上国では、貯蔵施設、物流、管理不備による腐敗などが原因となっています。
食品ロスとは、レストランや家庭での食べ残し、スーパー・コンビニなどの店舗での賞味期限切れなどで販売できず廃棄される食品です。2018年に発表された日本の食糧廃棄は年間2,842万トン(事業系2,010万トン、家庭系832万トン)で、食品ロスは646万トン(事業系357万トン、家庭系289万トン)となっています。
日本を含む先進諸国では飽食文化となっており、さまざまな肉が大量に消費されています。代表的な肉は牛肉、豚肉、鶏肉ですが、そのほとんどがトウモロコシなどの穀物飼育となっています。1kg当たりの肉の飼育に必要な穀物量はおよそ牛肉11kg、豚肉7kg、鶏肉4kgです。さらに、穀物栽培には水が必要です。間接的に必要な水量は、およそ牛肉20,600L、豚肉5,900L、鶏肉4,500Lと計算されています。この考え方を「仮想水(Virtual Water)」といい、他の食品1kg当たりの仮想水は卵3,200L、米3,700L、大豆2,500L、小麦粉2,100Lです。この考え方によれば、牛丼一杯を食べると仮想水1,900Lを消費することになります。日本の食糧自給率は38%程度であり、多くの食糧を輸入に頼っています。仮想水に換算すると、年間約800億立方メートル(80兆L)を輸入していることになります。これは日本が年間使用する水量とほぼ同じです。
(注)仮想水の計算にはさまざまな方式があり、一つの仮説です。

環境省のVirtual Waterを説明するページ
穀物生産の多くは地下水脈に頼っています。食糧生産の増大により地下水使用が増大しており、その枯渇が心配されています。現状のまま増産(そしてその30%が廃棄)されることになれば、2050年までには地下水の70%が枯渇するとの試算になっています。地球は水の惑星と呼ばれていますが、総水量の97.5%は海水であり淡水はわずか2.5%しかありません。さらに淡水の約70%は極地帯の氷として存在し、利用可能な淡水は0.8%で地下水が大半を占めます。地表の河川・湖沼の淡水はわずか0.01%しかありません。
もちろん、海水を淡水化すれば無尽蔵に水を使えますが、コストが膨大になり現実的ではありません。
水問題とは異なる観点で "Food System Shock" という考え方があります。温暖化(気候変動)により、土地の荒廃、砂嵐、バッタの大量発生などがさらなる土地の荒廃を引き起こすという悪循環により、2050年には生産量の10~15%が失われるという予測があります。主要農産物の輸出国は寡占化しており、生産量減少の場合には自国消費を優先し、輸出を規制が発動されます。日本のように自給率の低い国は、6ヵ月程度の備蓄ではたちまち食料危機に陥ることにもなりかねません。
このような危機を回避するためには、さまざまな対策と工夫が検討されています。

バッタの大群に襲われるアカシアの木 (出典:NATIONAL GEOGRAPHIC社WEB)
- 気候変動対策
- Global Food Supply Chain の改善による食糧廃棄・食品ロスの削減
- 化学肥料による大量生産の見直し(化学肥料により土地の荒廃が加速)
- 不耕起栽培(土地を深く耕さず下草維持により湿気を保持)による収量増大
(小規模農家でも増産可能でかつ持続生産が可能となる) - 食文化の見直しにより先進国で肉消費を削減(先進国では牛肉・豚肉消費を80%程度削減、日本でも70%程度削減が必要)。ノルウェーのEAT財団は、1日あたりの理想摂取量例として、全粒穀物(パンや米)232g、野菜350g、果物200g、乳製品250g、肉43g(牛肉・羊肉・豚肉14g、鶏肉・その他鳥肉29g)、魚28g、ナッツ50g、砂糖31gを推奨しています。
- 人工肉(代替肉)への転換。現状穀物生産の約1/3は家畜の飼料に使われていますが、人工肉への転換により直接人間の食糧としての供給が増加します。欧米では多くの企業が量産を始めていますが、スタンフォード大学教授が設立したImpossible Foods社は、肉を分子レベルで解析し、大豆を主原料にココナッツオイルを使い牛肉とほぼ同じ味を再現しています。この人工肉により、従来の牛挽肉と比較し、温室効果ガスは89%、仮想水は87%削減できるそうです。
日本でもバーガーキングが人工肉を展開し始めていますが、日本では歴史的に「精進料理」という素晴らしい食文化があります。

Impossible Foods社のホームページ
食料供給の歪みを10年以内に解決しないと、2050年時点で100億人に達するという地球人口の食を支えられないばかりか、日本でも食料危機が発生するとの警告もあります。このように極めて厳しい環境ですが、今年9月に「国連食糧システムサミット」が初めて開催される予定であり、2030年に「飢餓をゼロに」を達成するための最後の挑戦が議論されることになっています。
このサミットが成功することを祈るばかりです。
〈発行元/お問い合わせ先〉
株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
TEL : 045-444-5310
※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。
※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。



採択された17のグローバルな持続的開発目標