【JVCKENWOOD NEWS】
Through Tak's Eyes
サプライチェーンの重要性と脆弱性
日本船籍の大型コンテナ船がスエズ運河で座礁し、海上交通の大動脈を約一週間にわたって閉塞させたことは読者の皆さんにとっても記憶に新しいところです。日々の生活は人体における血流と同じく陸・海・空における昼夜のない輸送手段によって支えられています。島国の貿易立国である日本ではサプライチェーン(ロジスティクス)が極めて重要です。
では日本の貿易手段はどのようになっているでしょうか? 輸送量については、重量での測定と金額での測定があります。どちらの場合も輸出・輸入ともに海上輸送が圧倒的に多く、重量ベースでは全体の99%以上ですが、金額ベースでは77%となっています(2014年国土交通省資料)。
なぜ重量ベースと金額ベースで大きな違いがあるのでしょうか。海上輸送は輸送量を表すトンキロ(単位重量×輸送距離)あたりの輸送費が航空輸送より圧倒的に安く、重量が重くて単価の安いものは、海上輸送が選択されます。日本は資源の少ない国であり、石油や液化天然ガス(LNG)、石炭、鉄鉱石などの資源を100%近く輸入していますし、小麦や大豆など多くの食料も輸入に頼っています。また、日本が得意とする車や電化製品などの輸出も航空輸送は不向きで、海上輸送が基本であり、結果として重量ベースだと99%以上が海上輸送となっています。一方、金額ベースになると、貴金属など単価が高く軽量な商材では航空輸送が多く利用され、海上輸送の割合が77%と下がります。
輸出入の大動脈を担う海上輸送では、液体、原材料や梱包されない穀物などはタンカーやバルクキャリア(梱包されていない積み貨物を運ぶ船)によって運送されます。完成品や生鮮食料品などは通常コンテナに格納され専用船(コンテナ船)に搭載されます。コンテナ船は近年極めて大型化しており、今回スエズ運河で座礁した “Ever Given”は世界最大級の巨大船です。あえて「最大級」としたのは同クラスの船が複数存在するためで、すでに10隻以上就航しています。このクラスのコンテナ船の大きさは、船長400m・船幅59m・総トン数219,079トン・載貨重量198,886トンと、東京タワーより大きく、20,124個の20フィートコンテナを搭載できます。

“Ever Given”(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)
船の大きさを表す数字としてなじみがある「トン数」は、重量を表す場合と大きさを表す場合があります。
【大きさを表すトン数】
基本的に船の容積を表します。
- 総トン数:船内の囲まれた部分の全容積に係数をかけたもので、グロス・トン(Gross Tonnage)と呼ばれます。
- 純トン数:上記総トン数から航海に必要な区域の容積を差し引いた数値で、ネット・トン(Net Tonnage)と呼ばれます。貨物や旅客を載せる部分の区画容積を表します。
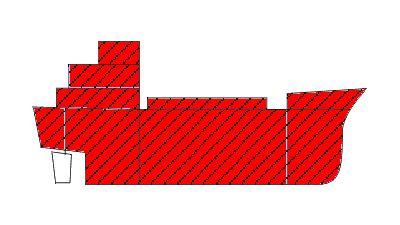
総トン数(出典:国土交通省中国運輸局)
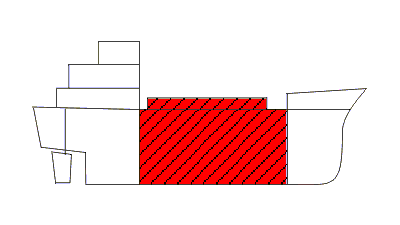
純トン数(出典:国土交通省中国運輸局)
【重量を表すトン数】
船の重さは「排水量(Displacement)(排水トン数とも呼ばれます)」で示されます。船の重量は「船が押しのけた分の水の重量に相当」(アルキメデスの原理)し、状態によって次の3つの排水量があります。
- 満載排水量:貨物・燃料などを最大積載した状態での船全体の重さ(Full Load Displacement)です。
- 軽荷重量 :貨物・燃料などを全く積んでいない状態での船単体の重さ(Light Weight) です。
- 載貨重量 :積載できる貨物・燃料などの総重量(Dead Weight)です。
ちなみに世界最大の船は “Mont“ というタンカー船で、船長458m・船幅69m・総トン数260,941トン、載貨重量564,763トンという巨大船でした。1979年に住友重工により建造されましたが、2009年に最後の航海を終えて解体されました。
軍艦としては、米国海軍の最新鋭の航空母艦ジェラルド・R・フォードが最大で、船長333m・船幅78m・満載排水量100,000トン以上あり、航空要員を含め4,660名により運用されています。建造費は当初62億ドルと見積もられましたが、電磁カタパルトなど新機軸を搭載したため最終的に約130億ドルに上昇しました。
最大の客船は”Symphony of the Seas”という豪華客船で、船長362m・船幅65m・総トン数228,081トンという巨体です。22ヵ所のレストラン、42のバーラウンジ、アイススケートリンク、複数の劇場などを備え、部屋数は2,759部屋、最大6,680名の乗船客を収容できます。まさに巨大なホテルが洋上を航海するようです。乗員も含めると約10,000人が居住する空間となっています。

“Symphony of the Seas”(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)
さて、話を戻しましょう。現在、コロナ禍でさまざまな影響が出ていますが、サプライチェーンも例外ではありません。港湾労働者の労働環境が制限されることにより、コンテナ船の洋上滞留(待機)が増加しています。その結果コンテナ船および世界に約1億8,000万個存在するコンテナそのものが不足する状態で、運賃が過去最高レベルに上昇しています。さらには足りないコンテナを航空輸送するという奇妙なことまで起こり始めています。このような状況ですので航空輸送も活況を呈しており、貨物機が足りないため旅客機の乗客席を撤去し、急ごしらえの貨物機として転用する航空会社も増加しています。コロナ禍で国際旅客数が激減している中、航空会社にとってはまさに「干天に慈雨」の状況かも知れません。
この難局を改善するためにはコンテナ船とコンテナの増産が必要ですが、コンテナ生産の96%は中国が占めており、増産を進めているものの、原材料や設備の納入遅れなどによりさらなる増産はできない状況です。また、海運業では対象船舶数が需要を下回れば、船価・船賃が上昇し、逆に上回れば下落する特徴が顕著に表れます。増産後、コロナが終息し平時に戻れば船価・運賃が急速に下落することも想定されますので、経営判断が重要です。そのような事情もあり、思い切った増産に踏み切れない要因の一つかもしれません。コロナ禍がいつ終息するか分かりませんが、一刻も早くこの状況が改善して欲しいと祈るばかりです。
〈発行元/お問い合わせ先〉
株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
TEL : 045-444-5310
※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。
※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。


